
「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ」。芭蕉の弟子、服部嵐雪(はっとりらんせつ)の一句ですが、この季節の様子をうまく詠んでいますね。寒い寒い背中を丸めて歩いていたけど、ちゃんと春は来てるんですね。このまま縁側に寝そべって、お茶でもすすっていたい・・・



二十四節気では雨水の季節にはいりました。『まるごと日本の季節』には「雪が雨に変わり、氷が溶け始めるころ」とあるので、一気に春めいてくるのかとおもいきや、数日前には雪がちらついたりと、まだまだ寒さがつづきそうです。しかも今週末は、今シーズン最強寒波が到来するんだそう。こんな日は特大マグカップにたっぷりコーヒーを淹れて、読書するのがいちばん。ということで、年末に翻訳者の下村純子さんにいただいた『フランス白粉の秘密』を手に取りました。以前ご紹介したエラリー・クイーンの国名シリーズ第二弾です。第一弾の『ローマ帽子の秘密』は劇場が舞台でしたが、今回はNYの百貨店で事件が発生します。
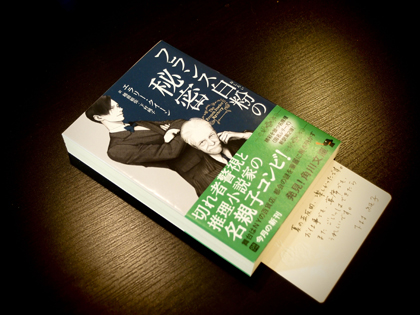
ミステリーなので・・・・・・やっぱりネタバレ厳禁ですよね。このシリーズはぜったいにTVドラマ向きだと思うんだけどなぁ。これを読んだプロデューサーさんっ、ぜひご一考を! エラリーは玉木宏さんとかどうでしょ。

〆切りが迫ると、ついつい夜型の生活になりがち。お仕事が手を離れ、ふと鏡を見ると、右頬に大きな吹き出物が。慌ててビタミン剤と塗り薬を買いに走りました。
今回お手伝いさせていただいたのは、『ストレスフリーの時間術』(日本経済新聞出版社)という本です。2月23日発売予定です。ストレスを溜めずに限られた時間を、自分なりにうまくコントロールする方法が紹介されています。仕事に私生活が振り回されている人、今よりも心穏やかに、あくせくしない人生を送りたい人は、なにかヒントが見つかるかもしれません。
「君とそっくりの人がでてくるから読んだ方がいいよ」と担当者に言われたんですが、自分とまったく同じ状況にあったグラフィック・デザイナーのシルヴィアのエピソードには思わず苦笑いしてしまいました。
本書のなかで、「自分を元気づけ、ストレスを減らす10のコツ」のひとつに、「好きなことに打ち込む」というものがありました。〆切り終わったし、しばらくうだうだ、ゆっくりしたいなぁ、と思っていたのですが、さっそく始めることにしました。
忙しくてしばらく放置していたこと…。それは買いすぎたタマネギの処理。一週間ほど前にスーパーで見つけた北海道産の大玉タマネギが7つ、ベランダに吊り下げたままだったんです。


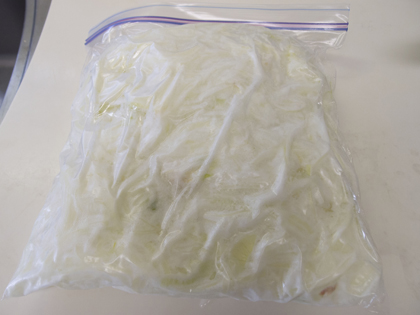




ここまでだいたい1時間くらいかかりましたが、気分的にはそこまで長くは感じませんでした。あまり深いことは気にせずに、ただ焦がさないように炒めるだけという単純作業が、ストレス解消に効いたのかもしれません。腐らせるかもしれない、っていう不安もひとつ消せたので一石二鳥。
残りのタマネギはあと4つ。ポタージュ用のタマネギも仕込むかな。タマネギの道はつづく。
週末は、新年あけて初の打ち合わせでした。電車にゆられて一時間。逗子はさわやかに晴れあがって、ちょっとした小旅行気分です。
ようやく発行の目処がたってきた『たのしい編集』。遅くとも3月には、出版にこぎつけられそうですで、ちょっとほっとしています。執筆はラストスパートといったところですが、翻訳家の越前敏弥さんや装幀家の大森裕二さんとの対談原稿は、初校があがってきたので、いまじっくりと読んでいるところです。しばらく時間をあけて読んでいるのですが、テープ起こしや原稿作成のときと比べても、同じくらい新鮮な気持ちで面白い! って思えました。もう少し、読者にわかりやすいようにならす箇所も必要ですが、内容はキレキレです。
校正を担当してくれる阿部さんには、「校正」の章にさっそく取りかかって頂いていますが、「この章に誤植あったら、まずいよねぇ」とプレッシャーが感じているご様子。でも誤植のない本なんて、存在しないっていうし、まあベストを尽くしましょう!
新企画の話やらもろもろで盛り上がってしまい、打ち合わせが終わったころにはもう九時半。あわてて今年初の潮騒料理・哉吉にくりだしました。
まずはお刺身から。今日のおすすめはメジナでした。鯛のような見た目なんですが、スズキ科の魚なんですね。ぷりぷりと弾力のある食感がたまりません。

刺身の下にひいてある、大根のツマがまたおいしいんです。すごく細くて、しゃきしゃきとした歯触りがくせになります。スライサーでつくったツマではこうはならないですよね。カウンター越しで、板前の重さんの桂向きをじっくり観察。紙のように透ける大根って、こんなに美しいんですね。自分でも何度か挑戦したことはあるんですけど、どうしても途中で切れちゃう。
「魚偏に安いと書くは春のこと」。この時期にははかかせません、鮟鱇鍋。あんなグロテスクな見た目なのに、なんて繊細な味なんでしょうね。骨のまわりの身をちゅっとすすって、柔らかい軟骨もこりこりと食べちゃいます。鮟肝は海のフォアグラとも呼ばれていますが、私はふつうのフォアグラよりもこっちのほうが好きかも。少しだけぬくまった鮟肝は、口のなかでとろけていきます。

カウンターから覗いてみると、立派ななまこが! なまこは赤なまこと黒なまこがあるらしいのですが、こちらは見た目どおり、赤なまこ。それにしても、これを初めて食べた人の勇気は賞賛すべきものですね。

がつんと真ん中を割ります。グアムのビーチにはごろごろと黒いなまこが転がってるんですが、いまだに触るのも気がひけます。

なまこ酢になりました! さばきたてのこの腸もしっかりいただきました。風邪がまだ完治していないので、ガラナジュースを飲んでいましたが、やっぱりこれは日本酒が合いますねぇ。
今日もおいしくいただきました。ごちそうさまでした。


馬鹿は風邪をひかないといいますが、どうやらその称号は返還せねばならぬようです。年末から薬を飲みつつ、だましだまし忘年会に参加していたツケが一気にやってきました。鼻水は止まらず、咽はびしびしと痛み、関節も思うように動きません。新年早々困ったことです。みなさまどうぞご自愛くださいませ。
食欲もあまりわかないのですが、薬を飲まないとやってられないので、無理矢理にでも食べないといけません。鼻と舌が馬鹿になってしまっているので、せめて食感だけでも美味しいものを味わいたいと思い、水餃子をつくりました。
まずは皮なんですが、いろいろなレシピを見てみると、薄力粉と強力粉の比率が気になりました。ほとんどの比率は1:1(もしくは中力粉)でしたが、「中国」と検索キーワードを入れてみると、1:2の割合が主流のようでしたので、今回はこちらを採用することにしました。ロシアやトルコにも餃子ににたような料理があるのですが、こちらは強力粉100%でつくるようです。簡単にいうと、のどごしの好みの問題らしく、もちもち食感が好きな場合は、強力粉の割合を増やしてあげればよいということ。そのかわり、捏ねる作業は強力粉が多めのほうが、体力が必要です。関節をみしみしいわしながら没頭しているうちに、身体の痛みを忘れてしまいました。(その代わり、しっかり熱は上がっていましたが)水の分量は、だいたい粉の半分ccと覚えてれば簡単ですね。今回は、薄力粉100グラム、強力粉200グラム、水150ccとしました。水には小さじ1.5杯ほどの塩をあらかじめとかしておきます。しっかりとつやがでるまでこね上げて、ラップできっちりつつんで放置しました。
餃子の餡は、本当はキャベツのほうが好みなのですが、正月に買った白菜がかなりしわたれていたので、必然的に白菜になりました。みじん切りした白菜を塩でころして、しっかりと水気を絞り、粘りがでるまで練り上げた挽肉に投入。生姜、ニンニク、ごま油、醤油、塩などで下味をつけました。
三時間放置した(二時間以上〜一日くらいだそうです)皮をさっと捏ねて棒状に整形し、金太郎飴の要領でカットしていきます。あらかじめ、生地を五本にわけて整形すれば、だいたい目分量で八分の一にカットできるので(つまり、8×5で40個できる計算)、簡単だったと、いまさらひらめきました。

皮は神経質になって伸ばしてはいけません。皮を食べる料理なので、少々厚めがおいしいです。私の好きな、横浜中華街の山東さんの水餃子も、このあいだ上海で食べた焼き小籠包も、餡より皮が主張していました。手の大きさにもよりますが、手の平サイズくらいが目安だと思います。金太郎飴状態の皮を手の平で潰し、だいたい丸くなったら、左手で皮を持ち、右手の麺棒で、外側から内側へ、すこし力をいれてころがします。あくまでも、外側から内側です。内側から外側へころがすときは、あまり力をいれない。外側の包む箇所が分厚いと、ゆであがったときに閉じた箇所が膨らんでしまって、とっても食べずらいし、食感が悪い。なのであくまで外側から中心へむかって生地をのばします。
ナイフで餡を押しつけるようにして(つまり空気をいれないように)はりつけ、好きな形に包みます。包み方はいろいろあるようですが、水餃子の場合、焼き餃子や点心に比べると、あまり形にこだわらなくてもよいような気がします。ゆであげたときに、けっこう歪な形のほうが美味しそうに見えるような。とにかくぎゅっと口を包むことだけが重要です。市販の皮よりよく伸びるので、包みやすいし、しっかりと閉じることができるはずです。
出来上がった餃子を、たっぷりの湯でゆがいて、餃子が表面に浮き上がってきたらびっくり水を一回。さらに沸騰させて、もう一度びっくり水。ふわふわと水面に上がってきたら食べ頃です。私はゆで汁とともに食卓に出します。
どうぞ熱々をお召し上がり下さい。
 これこそ寝正月の見本です。
これこそ寝正月の見本です。
 お年始に、日清フーズさんがだされている懐石を進呈させていただきました。急に目が覚めたご様子です。では、目が覚めているうちに、ひとことご挨拶を。
お年始に、日清フーズさんがだされている懐石を進呈させていただきました。急に目が覚めたご様子です。では、目が覚めているうちに、ひとことご挨拶を。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
12月に出版予定でした『たのしい編集』は、もろもろで執筆が遅れておりまして、ようやく装幀までたどりつくことができました。装幀をお願いする大森さんには、正月に対談の原稿のチェックをしていただきつつ、装幀を思案していただくという、鬼のような発注をしています。それにしても、シャレオツな赤い眼鏡がお似合いです。

紙を選んでいます
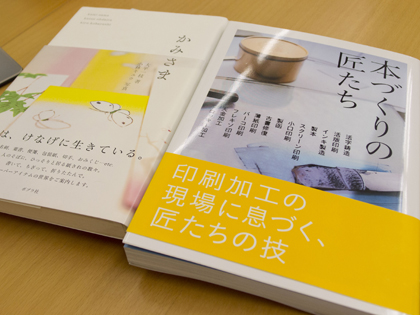
大森さんおすすめの二冊。
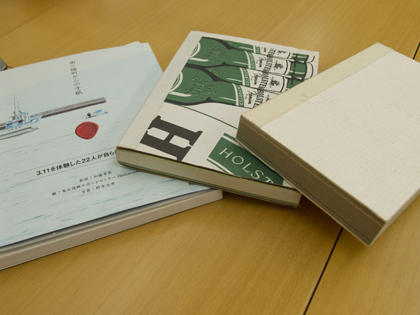
どれも凝ったつくりの本たちです

今年最後の阿津満

赤貝

青柳

鉄火巻き